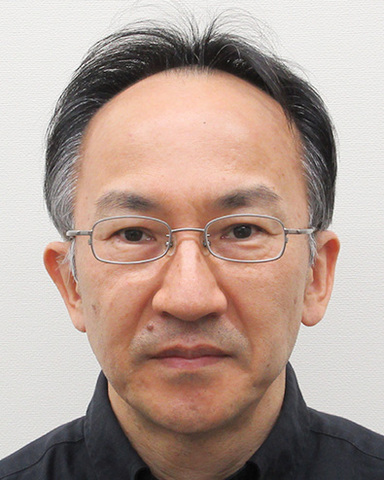特徴・特色
当科では口腔外科・口腔内科的疾患の治療ならびに有病者を対象とした一般歯科治療を行っております。総合病院ならではの、多数の疾患を持った患者さんをはじめ、当科を受診された患者さんのより良い口腔環境を維持していくため、患者さんの求めているものに耳を傾け、また、ご紹介頂いた先生のご意向に沿う治療を心がけております。また、手術までの待期期間を可能な限り短くしたいと考えており、初診から手術まで1か月以上お待たせすることがないよう、手術の枠を多く確保しております
口腔外科的疾患
口腔顎顔面外傷、顎口腔領域の腫瘍や嚢胞、埋伏智歯等の抜歯、歯の移植・再植、インプラント、顎関節症などの診断・治療を行っております。特に当科では歯の移植・再植を積極的に行っており、通常であればブリッジや義歯になってしまう症例についても、この手術を行うことによりご自身の歯でのかみ合わせの回復が可能ですのでお勧めしております。
手術の管理方法に関しましては全身麻酔、静脈麻酔、局所麻酔を選択できます。
口腔内科的疾患
口腔乾燥症、口腔粘膜疾患、唾液腺疾患、味覚異常、口臭等の診断・治療を行っております.
高齢者・要介護者・有病者の歯科治療、口腔ケアの指導
近年、高齢者、要介護者、有病者の健康問題の中で、食べることの重要性、ひいては老人の痴呆と咀嚼(かむこと)の関係がクローズアップされてきており、これらの患者さんの歯科治療、口腔ケアの必要性が高まってきています。従来、外来中心であった歯科治療も、全身疾患を持った患者さんを入院管理下で、他科との協力により歯科治療を行うケースも増加してきており、当科もこのようなケースを多く扱っております。
一般歯科
一般の歯科医院では治療が難しい持病をお持ちの方を中心に虫歯や歯周疾患の治療も行っております。一般の歯科医院で対応可能な患者様につきましてはかかりつけの歯科医院での治療を勧めさせて頂いております。
検査依頼
地域医療の二次的機関としての機能を発揮すべく、各疾患の治療のみならずCT,MRl,USG等の検査依頼も受けております。
静脈麻酔(静脈内鎮静法)について
当科では通常全身麻酔下で行うような手術に対しても、可能であれば静脈麻酔(静脈内鎮静法)を用いています。その理由は、入院期間が短く、仕事や学校など日常生活への影響が少ないこと、経済的負担が軽減されること、また全身麻酔に比較して、精神的・肉体的な負担が軽いことなどが挙げられます。
年間症例数は600例程度です。親知らずなどの抜歯、困難な抜歯、歯の移植や再植、嚢胞(のうほう)や腫瘍の摘出など、口腔外科の治療で通常より少し大変な治療を受ける方に最適です。また、歯科治療に対して恐怖心や不安がある方、吐き気を催す方、緊張で血圧が上がりやすい方などにも効果があります。
腕の静脈に点滴路を確保し、鎮静剤を少しずつ投与します。緊張感や不安感がほぐれて徐々に眠くなりますが、話しかけると会話できる程度の眠さです。リラックスした状態になってから、局所麻酔注射を行い、治療を開始します。そのため、血圧や脈拍数は通常より安定した状態で推移します。また、治療途中に会話はできるものの、会話や治療した内容をあまり覚えていないことがほとんどです。これを健忘効果と呼んでおり、多くの方が『治療のことをあまり覚えていない。治療のことを意識せず、楽にできた』と感想をおっしゃっています。
全身麻酔ではありませんが、これに準じた管理方法となりますので、術前に詳細な問診や検査(血液検査、心電図など)が必要です。また術中は血圧や脈拍数、パルスオキシメーターによる経皮的酸素飽和度、心電図などのモニターで監視しています。高齢者や有病者では酸素投与を行うこともあります。鎮静剤の効果がしばらく残りますので、術後は病棟のベッドでゆっくり休んでいただきます。
原則は1泊入院ですが、場合によっては日帰りでの手術も可能です。